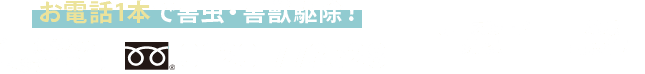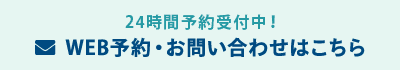京都を中心にゴキブリ、ネズミ、鳩などの害虫害獣駆除サービスを行っています、株式会社マイジョリティサービスです。「京都の害虫駆除.com」を運営しています。朝晩は過ごしやすい気温となり、季節の変わり目を感じている方も多いのではないでしょうか。この時期に気を付けていただきたいのがハチの巣です。今回は、夏場に巣を急スピードで成長させるアシナガバチについて解説します。こちらの記事を読んで、ハチについて正しく理解し、ケガなどに繋がらないように対策を行いましょう!
アシナガバチとは
<アシナガバチの見た目>
全長は12~26mmで、名前の通りスラリと長い足が伸びています。飛んでいる時にダラリと伸びた足が印象的で、素早い動きは得意ではなくフラフラ飛びます。
<アシナガバチの性格>
ミツバチに比べれば攻撃性が高いものの、スズメバチに比べれば攻撃性が低いハチです。基本的には、こちらから何もしなければ襲ってきませんが、直接危害を加えたり、巣に対して攻撃をしたりすれば襲ってくる可能性があります。
<主な活動時期>
例年、5月から11月頃まで活動していますが、特に夏場の6~8月ぐらいは巣作りに注力しているため非常に速いスピードで巣ができ上がってしまいます。
アシナガバチの巣の特徴
<アシナガバチの巣の見た目>
アシナガバチの巣はスズメバチの巣と違い、シャワーヘッドやお椀のような形をしているのが特徴です。色は灰色で最大で15㎝ほどの大きさになります。下から見ると六角形の穴が無数に空いていて、そのうちいくつかは白い繭でふさがっていることがあります。
<巣を作りやすい場所>
アシナガバチが巣を作るのは、ベランダや玄関の軒下、窓枠の影、エアコンの室外機の中など、雨風をしのげる場所が多く、室外機の中に蜂の巣が作られていたら、十中八九アシナガバチの巣と考えていいでしょう。このように、アシナガバチは家の周辺に巣を作る習性があるため、外に干しておいた洗濯物に紛れ込んでしまうという危険もあります。アシナガバチに気づかず洗濯物を取り込んでしまい、攻撃されたと勘違いしたアシナガバチに刺されるというような被害も多発しています。巣が作られていないかのチェックだけではなく洗濯物を取り込む前にもチェックしてください。特に6月~8月の時期は急スピードで巣が大きくなります。目立たない場所に作られた巣は、発見が遅れることも多いので、注意が必要です。アシナガバチの習性や特徴を詳しく説明した記事がございますので、参考までにご覧ください。

アシナガバチの巣を駆除するには?
まず、アシナガバチの巣を見つけた場合、もし自身で駆除を試みるのであれば事前準備をしっかりと行なってください。ハチにさされないように対策を行うようにすることが必要です。いくらアシナガバチの攻撃性が低いといえど、刺されるとアナフィラキシーショックを起こす原因となることがありますので、注意が必要です。アナフィラキシーショックとはハチに刺された時に起きるアレルギー反応のことです。一般的にハチに2回以上刺された場合に発症するといわれています。しかし実際には初めてハチに刺されただけで、アナフィラキシーショックになる方もいますし、複数回刺されても症状の出ない方もいます。アナフィラキシーの症状は様々ですが、代表的なものは呼吸困難や全身性のじんましん、血圧低下などがあります。特にショック状態に陥った場合は意識障害や、急激な血圧低下を引き起こし、最悪の場合は死に至る可能性もあるのです。はじめてハチに刺されてショック症状が出る場合は、一度に複数の個所を刺された場合に起こりやすいといわれています。また何度刺されてもショック症状が出ない場合もありますが、刺されるたびにアナフィラキシーになる可能性が高まるといわれています。このような危険性を回避するためにも、無理に巣の駆除をご自身で行うのではなく、業者に依頼することをオススメします。当社ではご自分で行われる方の為の防護服(下記の写真)の貸し出しをおこなっておりますのでご希望の場合はご相談ください。詳しくはリンクをご参照ください。
スズメバチ・アシナガバチ駆除に使用する防護服のレンタル行っております